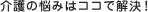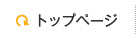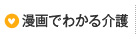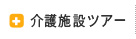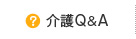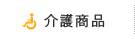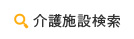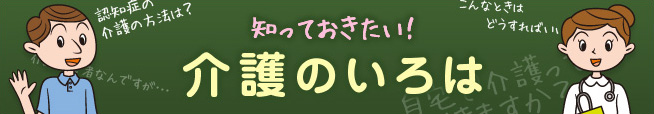
 介護のコツ その②
~自分の時間も大切にする(完璧派より長期派)~
介護のコツ その②
~自分の時間も大切にする(完璧派より長期派)~

高齢者介護が始まるとき、その原因はさまざまです。
ケガをして手足や腰が不自由になったり、骨粗鬆症で動けなくなったり、慢性疾患でベッド暮らしが長くなったり、そんなきっかけで高齢者の生活に手助けが必要になります。
あるいは、認知症によって1人では判断できなくなり、日常生活のサポートや介助が必要になったりします。
多くの場合は、年齢的な衰えから老化が進み、介護も長引くでしょう。
だからこそ、介護者は完璧な介護をしようと努力するのではなく、「長続きできる介護」を心がけましょう。

介護疲れ、悩んでいませんか?
長期にわたって介護を続けるには、やはり一人では難しいです。介護保険などの制度を利用し、ケアマネージャのアドバイスや地域のサービスを受けながら、その高齢者にあった生活を作っていきます。
このとき、誰でも「高齢者の生活をどうするか」(必要な介護用品をそろえたり、治療や手当の方法を探ったり)を考えます。しかし、同時に忘れてはならないのが「自分の生活も大切にする」ことです。
「○曜日は病院へ連れて行く」「○曜日は入浴の介助をする」「○曜日はデイサービスの日」など、介護にさく時間が増えても、できるだけ自分のためのスケジュールも立てましょう。
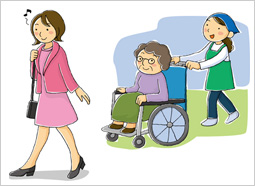
自分のためのスケジュールで気分転換♪
例えば、「趣味を続けたいから、デイサービスに行ってる○曜日○時は稽古をする」とか、「一週間に一冊くらい雑誌を見て気分転換する」とか、「洗濯物を畳むときコーヒーを入れて好きな音楽を聞きながらやる」とか。なにかひとつ“自分のための時間”を決めましょう。
もちろん、急な用事や高齢者の体調変化などで、せっかくのお楽しみタイムがとれないときもあると思います。しかし、もともと長期戦の介護生活です。今週がダメでも、来週のお楽しみにすればいいのです。
カレンダーが介護の予定でいっぱいになっても、違う色のペンで自分のお楽しみ予定も書き込みます。「このあたりで見たい映画のDVDを鑑賞しよう」など、希望でもいいのです。目に見える形で「自分のための予定」を書くことで、きっと前向きな気持ちで生活を続けられるでしょう。
(文:原 智子)
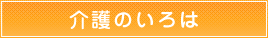
-
1. 介護のコツ

2. 高齢者の健康

3. 認知症の介護

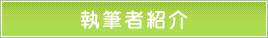
-

原 智子
<フリーライター>1968年生まれ、東京都在住。
タウン誌編集を経て、フリーライターとして雑誌で街情報などを執筆。
夫と夫の両親の四人暮らし。2010年から義父が認知症で、現在義母とともに介護に奮闘中。
介護のことで悩んだり失敗しながら生活していますので、みなさんの感想や情報も教えてください!
趣味は、天文・カーリング・サッカー観戦など。